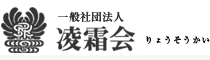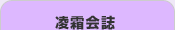凌霜第423号 2019年10月08日

凌霜四二三号目次
表紙写真 昭32営 小 澤 偉 伸 カット 昭34経 松 村 琭 郎
◆巻頭エッセー 「経済法」研究の半世紀 根 岸 哲 アフリカの産業発展とわが国の地方創生 大 塚 啓二郎 目 次 ◆母校通信 品 田 裕 ◆六甲台だより 行 澤 一 人 ◆本部事務局だより 一般社団法人凌霜会事務局 通常理事会で平成30年度事業報告及び決算書類など承認/第8回定時総会/ 臨時理事会/口座自動引き落とし、終身会費など便利な会費支払い方法の お知らせ/ご芳志寄附者ご芳名とお願い/事務局への寄附者ご芳名 ◆会費規定改定のお知らせ ◆一般社団法人凌霜会決算書 ◆新入会員/新入準会員 ◆凌霜会URL、ドメイン変更のお知らせ ◆第12回(令和元年度)社会科学特別奨励賞(凌霜賞)受賞者 ◆凌霜寄附講義を令和元年度も開講 ◆(公財)六甲台後援会だより(58) (公財)神戸大学六甲台後援会事務局 ◆経済経営研究所100周年事業と式典開催 濵 口 伸 明 ◆大学文書史料室から(32) 野 邑 理栄子 ◆学園の窓 法学研究科・法学部の課題 ⻆ 松 生 史 大学のこんなところが平成で変わった 下 村 研 一 経済学研究科におけるGMAPコースとIFEEKプラグラムの現状と今後の課題 西 山 慎 一 Whatʼs New Is Old Again 善 如 悠 介 ◆表紙のことば ノイシュバンシュタイン城 小 澤 偉 伸 ◆Trump or Tramp ? 檀 上 奎 吾 ◆古典和歌 ◆六甲台ゼミ紹介 法学部・大西裕ゼミ 大 西 朔 央 ◆学生の活動から 宝生流能楽部、復活の狼煙 藤森丈太郎・寺田伊織 令和元年度第40回神戸大学六甲祭開催のお知らせ 秋 山 由 奈 ◆六甲台就職相談センターNOW 令和の就活 浅 田 恭 正 ◆クラス大会 互志会 58 ◆クラス会 しんざん会、さんさん会、三四会、珊瑚会、イレブン会、 むしの会、双六会、神戸六七会、よつば会、 フォーティナイナーズ(49ers)の会、61会 ◆支部通信 東京、石川、大阪、神戸、鳥取県、愛媛県、デトロイト ◆つどい 竹中ゼミ、ホッケー部東京OB会、宝生会、 男声合唱団グリークラブ、凌霜謡会(観世流)、 凌泳会、二水会(バレーボール部OB会)、 シオノギOB凌霜会、水霜談話会、大阪凌霜短歌会、 東京凌霜俳句会、大阪凌霜俳句会、凌霜川柳クラブ、 神戸大学ニュースネット委員会OB会 ◆ゴルフ会 芦屋凌霜KUC会、廣野如水凌霜会、能勢神友会、 垂水凌霜会、花屋敷KUC会 ◆追悼 永井正彦さん(昭37経)を偲んで 大 橋 政 之 ◆物故会員 ◆国内支部連絡先 ◆編集後記 行 澤 一 人 ◆投稿規定 巻頭エッセー
「経済法」研究の半世紀
神戸大学社会システムイノベーションセンター特命教授 日本学士院会員 昭40法 根 岸 哲
私の「経済法」研究は、すでに半世紀を超えている。昭和40(1965)年3月、法学部を卒業し、司法修習生(第19期)を経た後、昭和42(1967)年4月、法学部助手に採用され、「経済法」とは何かをほとんど知らないまま研究を開始することとなった。 「経済法」との出会いは、4年生後期、ゼミの先生であった民事訴訟法の山木戸克己先生から、「経済法」の福光家慶先生をご紹介いただいたことによるものであり、全く想定外であった研究者への道に足を踏み出すことになった。 私が「経済法」の研究を開始した当時、「経済法」講座のある大学はほとんどなく、研究者も少なかった。「経済法」の研究は、戦前から経済統制法を中心として行われていたが、戦前、「経済法」講座を設置していたのは、神戸大学(神戸商業大学)と一橋大学(東京商科大学)だけであった。戦後は、農地改革、労働運動の解放、財閥解体とともに、占領政策である経済民主化政策の柱として、昭和22(1947)年、「公正且つ自由な競争を促進し、一般消費者の利益の確保と国民経済の民主的で健全な発達の促進」を目的とする独禁法(法律の正式名称「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)が制定されるに至り、戦後の「経済法」は、自由経済体制ないし市場経済体制の基本である競争のルールを定める独禁法を中心として展開されることとなった。独禁法は、米国反トラスト法(米国独禁法)を母法とするものであった。 しかし、独禁法に対する社会の支持は、制定当初から、極めて薄いものであった。(1)戦勝国の米国に押しつけられた法律である、(2)明治以来の国家主導型ないし官民協調型の経済運営とは相容れない、(3)伝統的に和と協調を美徳としてきた日本社会になじまない、などとして歓迎されなかった。また、いわゆる左派陣営からは、時代を反映して、修正資本主義を延命させる「反動の法」である、などと批判されていた。 このような状況を反映して、私が研究を開始した当時の「経済法」は、文字通り諸法雑法の末端に位置する、いかがわしい法分野にすぎなかった。私は、生来、天の邪鬼のところがあり、むしろ、それならやってみようと考えた。それなら、私でもできるかもしれないというのが正直な思いでもあった。 いわゆる助手論文を2年以内に提出するよう求められ、四苦八苦の末、ようやく辿り着いたのが「規制と競争」というテーマであり、米国の運輸(陸運、航空、海運)事業規制と競争との関わりを探り、日本の問題解決に参考にしようとする論文を書き上げ(でっち上げたというのが相応しいかもしれない)(神戸法学雑誌19巻1・2号、3・4号)、有り難いことに助教授にしていただいた。さらに有り難いことに、1ドル360円の時代に、神戸大学六甲台後援会の援助をいただき、米国カルフォルニア州立大学バークレーのロースクールに客員研究員として留学させていただいた(20年後の論文集『独占禁止法の基本問題』(有斐閣平成2(1990)年の刊行も六甲台後援会の援助によるものである)。生半可な留学生活にとどまったが、この留学経験はその後の私の大きな財産となっている。いわゆる留学の成果と称して、独禁法と経済学(産業組織論)との関わりを探る論文と、当時日本にはまだなかったクーリング・オフの権利に関する消費者法に属する論文を発表することもできた。 私が帰国した後も、独禁法を中心とする「経済法」の「冬の時代」は続いていた。渋々にしろ、その状況が変化するのは、外圧によるものであった。直接的かつ最も強力な外圧は、昭和の終わりから平成の始めにかけて行われた日米構造問題協議(Structural Impediments Initiative(SII) talks)であった。これにより、公的な輸入障壁としての規制の撤廃・緩和(規制改革)と、民間の輸入障壁としての企業間の競争制限的な慣行の廃止に向けた独禁法の強化とが進行することとなった。間接的な外圧は、国際的に事業展開する日本の大企業において、カルテル・談合などに手を染め、諸外国・地域において厳しい制裁を受けることが多くなり、また、大型のM&Aに当たっては、独禁法の執行当局である公正取引委員会のみならず、諸外国・地域の競争当局(独禁法は、国際的には、米国反トラスト法を含め競争法と呼ばれる)への事前届出と審査を経る必要があり、それらが独禁法の重要性を認識させることとなった。 導入までに日時を要し、「仲間を売る」ことになるとして、その利用に強い抵抗感が示されていたカルテル・談合に係る課徴金減免制度(カルテル・談合の参加の事実をいち早く公正取引委員会に申告すると課徴金が減免される制度。世界各国・地域の競争法においては、以前から、leniency programとして知られていた)も、今日では、名だたる大企業が率先して利用するに至っている(嘆かわしいことかもしれない)。今や、「経済法」は、司法試験の選択科目の一つになり、選択する受験生も多い。独禁法を専門とする弁護士の国内外における活躍もめざましいものがある。最近では、デジタルプラットフォーマーとしてのグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン(GAFA)の個人情報に係るビッグデータを駆使した企業活動、コンビニの24時間営業を含む本部と加盟店との関係、芸能事務所と個人事業主である芸能人・タレントとの取引関係などに独禁法のメスが入るかといった報道が連日のようになされ、いかにも独禁法を中心とする「経済法」の重要性・存在感を示しているようにもみえる。私は、独禁法を中心とする「経済法」の長い「冬の時代」の経験者であるトラウマか、このような動きがしっかりと根を下ろした本物であるのか、なお疑っている(注)。 しかし、このような時代の変化があったのであろうか、私は、昨年12月、日本学士院の会員に選出された。「経済法」単独の専攻者としては初めてのことである。全く思いがけない出来事であり、個人的には誠にお恥ずかしいというのが正直な実感である。しかし、「冬の時代」が長かったにもかかわらず、独禁法を中心とする「経済法」の研究を支えてきた研究者仲間の活動が社会的に認知されたものと受け取り、大きな喜びも感じている。 私の「経済法」との出会いは全くの偶然であったが、半世紀以上もの間、飽きもせず「経済法」の研究に携わってきた。その理由は、一言でいえば、独禁法を中心とする「経済法」の研究が面白かったからである。なぜ面白いかというと、第一は、重厚長大型産業から軽薄短小型産業まで、ハイテク産業からローテク産業まで、あらゆる産業分野に適用される一般性である。第二は、経済や産業が不断に変化するのに対応して適用のあり方が変化する、飽きることない不断変化性である。第三は、元来、行政法、民事法、刑事法の総合法であり、今日では、知的財産法、消費者法、労働法、個人情報保護法などとの相互補完関係が注目される法学分野横断性・総合性である。第四は、元来、法と経済学の混合物といわれてきたが、マーケティングや経営学との協働も不可欠となっている学際性である。第五は、企業活動のグローバル化に伴い、国際的な企業買収、ウインテル帝国を構成したマイクロソフトやインテルの事件、最近ではGAFAの事件やクアルコムの事件など国際性の高い事件が目白押しであり、それ自体きわめて好奇心を満足させてくれるとともに、比較法的見地からも宝の山となっている国際性である。しかし、面白かったなどというのは、もはや研究業績を気にする必要がなくなったからであり、後知恵にすぎないのかもしれない。今も面白いというのは、老害の最たる証かもしれない。
(注)つい先日、六甲台図書館の学生用に便利になっている開架式図書室に入室し、多くの学生が勉学に励んでいることに驚いた(?)が、それ以上に驚いたのは、国会図書館日本十進分類法が、「経済法」を法律ではなく経済に分類していることを発見したことであった。米国留学中に、専門分野は何かと問われたときに、Economic Lawと答えたところ、経済法則かと返されたことを想い出した。
筆者略歴 昭和18年3月23日、神戸市垂水区生まれ。昭和40年3月神戸大学法学部卒業。昭和40年4月司法修習生。昭和42年4月神戸大学法学部助手、昭和53年4月神戸大学法学部教授、平成12年4月神戸大学大学院法学研究科教授。平成18年4月神戸大学名誉教授。平成18年4月甲南大学大学院法学研究科法務専攻教授。平成28年4月神戸大学社会システムイノベーションセンター特命教授。平成30年4月甲南大学名誉教授。 巻頭エッセー
アフリカの産業発展とわが国の地方創生
神戸大学社会システムイノベーションセンター特命教授 日本学士院会員 大 塚 啓 二 郎
私の専門は、開発経済学である。研究者として駆け出しであった1980年代には、アジアの途上国の研究をしていたが、アジアでは経済が急速に発展している一方で、アフリカは停滞しているという現状を見て、1990年代になると徐々にアフリカの研究に乗り出すようになった。2000年を過ぎてからは、貧困にあえぐアフリカ(特にサハラ砂漠以南のアフリカ)の研究に完全に軸足を移し、少しでも貧困削減に貢献すべく、現地密着型の実証研究を続けてきた。新参者のアフリカ研究者としての私の利点は、日本の明治以来の経済発展の経験、そして戦後の「奇跡」とも言われる東アジアの発展の経験を知っていることにある。なぜならば、「アジアはアフリカの未来」だからである。 この地域では、食糧が不足気味である。特に最近はコメの消費が伸びていて、1人当たりの消費量は日本人の半分くらいの水準にまで達しているが、生産が追い付かず、アジアからコメを大量に輸入している。しかし、アフリカには湿地が多くあり、水稲の生産に適している未利用の土地が沢山ある。そうした湿地で、熱帯アジアで栽培されている高収量品種を栽培すれば、アジアに負けない収量が上がる。しかし、それは実現していない。なぜか? 私の答えは、人材不足とその結果としての技術導入の失敗である。アジアの水稲品種とアフリカの環境に適した在来の水稲品種をかけ合わせれば、もっと優れた水稲品種が開発できるはずであるが、それができる稲の育種の専門家はアフリカにはほとんどいない。水稲栽培は、種子の選別、耕起、育苗、水田の均平化、移植、除草、水管理等、かなり複雑であるが、栽培技術を熟知しそれを水稲農家に伝えられる農業普及員はアフリカにはほとんどいない。こうした状況では、水稲栽培に精通した篤農家もいない。その結果、畔すら作らないような「荒らし作り」が行われている地域もあり、1ヘクタールあたりの水稲の収量は2トンをわずかに超える程度である。明治の初めの日本の収量は3トンに近かったから、これは明らかに低い。こうした状況では、肥料に補助金を出したり、融資制度を充実させても、効果は期待できない。水稲栽培を発展させるためには、農業科学者、農業普及員、指導的農家の育成と、彼らによる海外からの(特にアジアからの)技術導入が不可欠であり、それを支える制度が必要である。 それを実現するために、私はJICA(国際協力機構)が実施している「アフリカの稲作振興のための共同体(CARD)」を支援してきた。うれしいことに、私の助言に応じてCARDが目標として定めた「10年間でコメ生産を倍増する」は、2018年に達成された。とは言え、アフリカのコメの生産性は依然として低く、さらなる増産のためには、人材育成と技術導入がますます重要になっている。 アフリカでは、都市での「仕事」が不足している。農業は雇用吸収力が弱く、増大する人口は都市に集まってくる。しかしながら、工業化、すなわち製造業の発展に失敗しているので、アフリカの都市には収入のいい仕事が極端に少ない。仕方なく、収入の低い「物売り」に従事したりする人々がいる一方で、失業している人々も多い。そうした状況では、犯罪率が高く治安が悪い。 「ICTを導入してイノベーションを起こそう」と、考えるアフリカの政治家や先進国の援助の専門家は多い。しかし、ICTを使いこなせるのは一握りの高学歴の人々だけである。ICTの活用が貧困問題の解決につながらないことは、インドやフィリピンの経験が如実に示している。 賃金の低い非熟練労働者が多い状況では労働集約的な産業を発展させ、教育水準が高く良質だが賃金の高い労働者が豊富にいる状況では知識集約的な産業を発展させるというのは、経済発展の鉄則である。日本をはじめとする東アジアの経済発展の経験は、この鉄則の重要性を示している。今アフリカで必要なのは、労働集約的な産業を発展させることである。それでは、どうしたらいいのか? 私の答えは、人材育成であり海外からの知識の導入である。人材を育成し、海外からの技術導入を積極的に行って経済発展に最初に成功した途上国は、言うまでもなく日本である。つい最近まで驚くべきスピードで発展してきた中国も、今や先進国となったシンガポールも同じ道をたどった。 人材育成には、学校教育が重要であることは言を俟たないが、研修も重要である。私自身は、日本流の経営システムであるカイゼンをアフリカで普及することを目指している。エチオピアでは、切れ者として名高かった故メレス首相と議論し、「カイゼン研修所」の設立にこぎつけた。この首相は、なんと在職中に博士論文を執筆していたという研究肌の政治家であった。この研修所では、日本のカイゼンの専門家を招いて、エチオピア人のカイゼンの専門家の育成を行っている。カイゼンの重要性はエチオピア全土に知れ渡るようになり、徐々にカイゼンが経済全体に浸透する気配である。 エチオピアの悩みは、せっかく育成したカイゼンの専門家が民間企業に引き抜かれてしまうことだという。しかし、これは当初から織り込み済みだ。研修を受けて実力を付けた人材は、自分の能力を最大限に発揮できる仕事を求めるし、誰もそれを止めることはできない。逆に言えば、研修は利潤追求型の私企業に任せきることは出来ないのである。転職してしまうことを恐れて、私企業は従業員の人材育成に消極的な傾向があるからである。しかし、転職によって適材適所が実現すれば、経済全体にとっては大きなプラスである。だから、人材を育成し、海外からの技術導入を実現するためには、産業全体の利益を考える同業者組合のような組織が力を発揮することが多い。また、経済全体の利益を考えながら、そうした組織の活動を支えるような政策が必要なのである。 私自身は、失業率が27%と驚くほどの高水準で、仕事の不足に悩まされている南アフリカで、カイゼンの普及を推進するための研究に着手したところである。当面の目標は、カイゼンを採用することが、いかに企業の生産性と採算性を引き上げるかを数値で示し、南アフリカの企業家にカイゼンの重要性をアピールすることである。その第一歩として、自動車産業、特に地場の下請部品企業を研究対象にしている。 途上国の研究ばかりに没頭してきた私であるが、最近、日本の地方の発展問題が気になるようになってきた。アフリカと同じく、日本の多くの地方は産業と仕事の不足に悩んでいる。その結果、人口流失に歯止めがかからず、地方は衰退しつつある。でどうしたらいいのか? ここでも鍵は、人材育成にあり、「外部」からの新しい知識の習得にある。モノとカネと情報が自由に世界中を飛び回る現代の世界においては、地方といえども世界と戦えるような産業を育成しなければならない。そのためには、国際水準の人材が欠かせない。そうした人材なくしては、地方創生はまさに絵にかいた餅に終わるであろう。アフリカと違うところは、賃金の高い日本では、知識集約的な産業を発展させなければならないということである。そのためには、大学・大学院の活用は必要不可欠である。最先端の科学的知識、コンピュータ技術を駆使した経営、経済の論理に立脚した開発戦略は、必須項目である。だから、世界が見渡せる賢い経営者、賢い政治家や官僚が必要である。 それにしても、「無」から産業を興すのは至難の業である。私のアフリカでの戦略は、すでに存在している産業を見つけ出し、人材育成と技術導入によってそうした産業を発展させようとするものである。政府の支援もないのに、たとえ細々であっても、産業が芽生えているということは、その産業に何らかのメリットがあるからに他ならない。そうした産業は潜在的には有望であり、カイゼンを指導し、ステップアップを図ろうというのが、私の狙いに他ならない。 日本の地方の場合にも、まず芽が出かかっている産業を見つけ出す必要がある。身近に感じるのは、地元神戸の医療クラスターである。そこに進んだ経営方式を導入し、経済学に立脚した発展戦略を練り、最新の医学を適用すれば、このクラスターは爆発的に発展できるだろう。最大のボトルネックは、そうしたことに気づいている政治家や官僚の不足である。日本経済にとって大学院の充実を通じた研究の促進や高度な人材育成が決定的に重要になっている今日、それを指摘する賢い政治家や官僚は日本にはほとんどいない。その点でも、アフリカの発展とわが国の地方創生には大きな共通点がある。 |