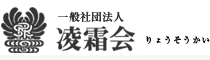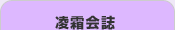凌霜第386号 2010年08月01日

◆巻頭エッセー
ウイーン売買条約と法学教育の平成維新 齋藤 彰
◆母校通信 田中 康彦
◆六甲台だより 吉井 昌彦
◆理事長からのメッセージ8
「新しい凌霜会への歩み(その2)」 高崎 正弘
◆学園の窓
育児休業中のことなど 浦野由紀子
在フイリピン日本大使館勤務を終えて 片山 裕
所属の決め方 宮川 栄一
「平成24年度入試より新たに
推薦入試制度を開始します」 山崎 尚志
◆国際模擬商事仲裁を体験して 藪 恭兵
◆リレー・随想ひろば
ポテト会 山崎 二朗
サイゴンの思い出 森山 徹
「婦人ボンド」の思い出 辻 雄史
大学院社会人コースでの2年間 藤井 恵
東京で「神戸コレクション」 三浦 彰太
◆本と凌霜人
「ソロバン先生英国を行く」 手塚 邦夫
「だから、日本って変」 本田 忠生
「改訂版 初歩からのマクロ経済学」 東 秀行
「後期高齢者医療制度を再考する
豊かな長寿社会に向けての13の提言」 田村 匡
凌霜俳壇 凌霜歌壇
<抜粋記事>
■ウィーン売買条約と法学教育の平成維新
法学研究科教授 齋 藤 彰
2009年8月に国際売買について世界の法律を統一する「ウィーン売買条約」が日本で発効した。この条約には現在74カ国が加盟しており、すでに世界の貿易大国はほとんど加盟していた。例によって日本は大きく出遅れたことになる。ウィーン売買条約が発効して1年間が経つ現在、それが日本の法律実務にどのような影響を与えているのかを皆さんに伝えるのが本稿の執筆依頼の趣旨であった。しかし、これまでのところウィーン売買条約を日本の裁判所が適用した事例は報告されていない。つまり実践的な意味では、期待は空振りに終わっているのが実情である。
しかし法律学のグローバル化に関して、私には読者の方々に伝えたいことがいくつかある。まず、今年の5月に行われた新司法試験の選択科目の1つである「国際関係法(私法系)」において、この条約の空間的適用範囲について、かなり深い理解が必要とされる出題がなされた。つまり法科大学院は、最早ウィーン売買条約を避けて通れなくなった。
さらに、模擬国際商事仲裁大会への日本も含めた参加校の急増が見られた。この大会では毎年ウィーン売買条約の適用される事件が取り上げられる。今春の香港大会には日本から神戸大学を含む5つの大学がチームを送り出した。これは過去最多であり、来年はさらに日本から2大学が加わる予定である。今年の香港大会には世界中から75大学が、ウィーン大会には251大学が参加した。本条約に加盟していないインドやイギリスのチームもすでに参加している。両大会へ最多のチームを送り出しているアメリカでは、ウィーン売買条約の適用を排除する契約慣行が強く根付いている。条約への加盟の有無や実務状況を問わず、世界中で法律を学ぶ学生にとって、ウィーン売買条約の影響力は着実に、そして極めて強いものになりつつある。
こうした法学教育のグローバル化は、ごく一部で例外的に生じている現象だろうと想像される方は少なくないであろう。実際に、日本の法学教育をグローバル化の波が直撃したことは、これまでなかったと思う。しかしつい最近になって、私は根本的に認識を改める必要性を実感する事件に遭遇した。それはパリ第一〇大学で法律を専攻する大学院生3名を、この4月から法学研究科が受け入れたことに始まる。もちろん、世界各国の大学が学術交流や学生交換を行うための協定を締結することは古くから行われてきており、パリ第一〇大学も神戸大学と協定を結んでいる大学の1つに過ぎない。しかし、こうしたパリからの学生の受け入れは、これまでと一線を画すものであった。なぜなら、そのうちの2人はほとんど日本語が話せない学生であり、また残りの1人の受け入れにもこれまでに経験したことのない苦労があった。なぜそうした留学生を大胆にも法学研究科が受け入れたのか?それにも教育のグローバル化に伴う事情がある。神戸大学からは既にかなりの数の学生をパリ第一〇大学に送り出してきた。これに対しパリ第一〇大学側が交換留学生を推薦してきたのは今回が初めてであり、借り越しの状況にある神戸大学は受け入れを拒否することができなかった。しかもその3名が全員、どういう訳か神戸大学の法学研究科を留学先として選んでいた。
現在欧州の多くの国では、学生の流動性を高めるために、学部教育を3年間とし、その後の2年間をマスター(修士課程)として、それをさらに2分割し、マスター1・マスター2とする制度へと移行している。3名の内1名はマスター1と呼ばれる課程に在籍している。パリ第一〇大学のマスター1は完全な講義制で、1年間の前期・後期においてそれぞれ7科目を履修する。半年間日本に留学するに際し、その学生はパリの留学コーディネータと相談し、神戸で受講する講義科目すべてを決定し来日した。しかし法学研究科では、教員の事情などによって時間割が昨年とかなり大きく変更された結果、予定通りの履修が不可能となっていた。そのため、私はこの学生の受講科目の調整手続にかなりの手間と時間とを費やした。
しかし私にとってさらに衝撃的だったのは、パリに半年しか居らず、残り半年を神戸で過ごし卒業単位の半分を神戸大学で取得する学生に、パリ第一〇大学が躊躇なくマスター1の学位を与えることであった。これを交換協定大学間の相互的信頼に基づく措置といえば聞こえは良い。しかし単純に表現すれば、自校の学生の教育の半分を、神戸大学に「丸投げ」しているわけである。また、日本語ができない他の2人の留学生は、マスター2の学生であり、1年間の神戸大学留学中に本格的な研究指導を求めている。
こうした大胆な学生の国際流動化促進は、欧州連合で展開されてきたエラスムスというヨーロッパ域内での学生流動化を高める奨学プログラムの波及効果である。教育制度の枠組みを共通化し、その枠組みをフル活用し学生をどんどん各国へと自由移動させていく。そうした流れが、ついに欧州の枠をも超えて日本の大学にまで達したといえよう。
法学教育の英語化は、交換留学と関連して、法学研究科内で何度も議論されてきた。しかし法律科目の教員には躊躇があり、それは正当なものであったと思う。法律学は基本的にローカルな学問である。そして、日本の法律家が日本語で法律を論ずる以上、日本語による法学教育の必要性が減少するとは考えがたい。また、日本での学位取得を目的とする長期の留学生は、当然に日本語で法的議論を行う能力を身につけることを真剣に考えている。しかし半年あるいは1年間だけ日本で過ごす外国人の交換留学生にとっては、多くの講義が英語で提供されることが望ましい。
こうした矛盾する要請のすべてに私たちが対応するのは無理である。名案はないかと考えあぐねていたが、実践可能な対策をやっと1つだけ思いついた。概要は次の通りである。まず目標設定であるが、これから5年間を目途に神戸大学法学研究科の講義全体の10~15%を英語で行うことを目指す。しかしそのほとんどは、日本人教員が行うのではなく、海外の様々な大学から招いた教員によって行われるようにすればよい。例えば中国の大学教員が神戸大学で中国法を英語で講義し、それを留学生と日本人学生とが一緒に聴くようにすれば一石二鳥である。
実はこの5月、欧州の国際私法に関する集中講義がスコットランドから招いた2人の教師によって神戸大学で行われた。受講者の約半数が留学生であり、残り半分が日本人大学院生となった(残念ながら、欧州法を扱うこの講義はパリからの留学生には魅力に乏しいものであったが)。まだ学部生で英語の講義について行くだけのリスニング能力を持つ者はごく少数である。多くの日本人学生諸君に、この壁を何としても早く突破して欲しい。
こうした講義は受講者には概して好評である。法律は社会文化の一面であり、それぞれに際だった個性があり、そして独自の強みと弱みとがある。海外の法制度に触れることは新鮮であり刺激に満ちている。社会や人間に対する深い洞察力の養成にもつながるであろう。そして何よりも、海外からの教員による英語の授業では、そうした講義を受講する全ての学生が広く教育グローバル化の恩恵を享受できる。
それでは私たち日本人教員のグローバル化は、どう考えるべきであろうか?その反対を、つまり私たちが海外の大学に出向いて日本法を英語で教えることを行っていけばよい。そうした授業の潜在的需要が存在することは、海外の学生や研究者の日本法への関心からも明らかである。また海外の大学で、日本語の分からない学生に対し英語で講義をするのであれば、それは私たちにとっても、新鮮でやり甲斐ある経験となろう。もちろん、こうした法学教育のグローバル化に向けた展開には、それなりの資金が必要であるが、その中心は海外教員の旅費滞在費である。たとえば凌霜会がスポンサーとなる場合には、「凌霜レクチャー」とでも名付ければ、学生諸君が凌霜会のもつ意義を認識するよい機会となるであろう。
筆者略歴
神戸市出身、昭和54年神戸大学法学部卒業(西原ゼミ)、大阪商船三井船舶(当時)勤務の後、昭和63年神戸大学大学院法学研究科単位取得、平成2年アバディーン大学(スコットランド)LL・M。摂南大学法学部講師、関西大学法学部助教授、教授を経て、平成13年神戸大学法学研究科教授。ローエイシア・ビジネス法教育常設委員会委員長。
■理事長からのメッセージ 8
「新しい凌霜会への歩み(その2)」
社団法人凌霜会理事長 高 正 弘
季節の移り変わりは早いもので、盛夏を迎えることとなりましたが皆さまにはお変わりなくお元気にお過ごしのことと存じます。
さて、前号でお知らせしました「新しい凌霜会への歩み」の推進力となります新組織は4月1日に予定通りスタートし、関連する施策が始動しましたので以下その現状をご報告します。
Ⅰ 去る5月28日に役員会、評議員会・会員総会が開催され、①一般社団法人への移行を目指す「凌霜会」の定款暫定案、②21年度事業報告・決算及び22年度事業計画・予算案(新法人移行のための特別対策費を含む)、③理事・監事、評議員の改選案、の3議案が審議・承認されました。
① 定款暫定案は、新「凌霜会」の憲法素案であり、新法人移行に向けた当局との事前折衝のベースとなるものです。今後、付帯する諸規則案の整備と当局との事前折衝を並行して行い、来年の総会までに成案を固め役員会等の承認を得る。その後、法律上の期限までには少し余裕をもって23年度の適当な時期に移行認可申請を行い、24年4月1日の法人登記完了、新法人スタートを目指すことになります。
② 21年度事業報告・決算書類および22年度の事業計画・予算案については、本誌公告および凌霜会ホームページをご参照下さい。数値に関連して特にご理解いただきたいのが次の3点であります。
・ここ数年赤字が続いていた期間損益は、関係者の会費収入増強と事務合理化努力によって、正味財産増減計算書にあるように、新法人移行のための特別対策費を除くと前期は収支均衡を達成することができました。今年度収支予算も、特別対策費控除前では若干の黒字確保を前提として作成されています。勿論、現状に満足することなく、法的に義務付けられる公益目的支出計画の堅確性を高め、かつ、移行後の組織の活力を維持するためには、それ相応の黒字を安定的に確保していかなければならないことは言うまでもありません。
・会費収入面では、準会員の皆様からの会費収入のウエートが年ごとに高まってきています。準会員向け施策の充実を更に進めなければなりません。
・支出面では、事業費の約50%を会誌発行費が占め、凌霜会活動のなかで如何にこの事業のウエートが高いかを示しています。会誌内容の一層の充実が求められています。
③ 理事・監事、評議員の改選については、新法人への移行の過渡期でもあり異動は最小限に留めることにしました。即ち、理事数は3名減の22名、評議員は13名減の222名で今期をスタートすることになります。勿論、両組織とも定款に定める定員水準は確保しています。
Ⅱ 安定した収支の礎となる「組織の活性化」、「身近な凌霜会の実現」に向けては、その第一弾としての準会員向け「セミナー」が、去る5月19日、昭和45年に経済学部を卒業された阪神電気鉄道株式会社の坂井社長様を講師にお迎えして予定通り開催されました。
大学におけるキャリア教育の必要性が叫ばれています。絶えず在学生諸君のニーズを汲み取りながら、「継続は力なり」をモットーに活動内容の充実に努めてまいります。
一方、会員増強の決め手となる入学手続き時の入会勧誘態勢は、大学事務局のご協力も得て今年から全学ベースで一層整備されました。過日の学友会幹事会でその成果の一部が報告され、併せて、来年度に向けての協議を更に進めることを確認したところであります。
以上のように新法人への移行準備は課題を明確にしつつ順調にスタートしましたが、所期の目的完遂に向けて、今後とも公益法人改革対応新組織の切れ目のない活躍に負うところが大であります。会員各位のご理解と幅広いご支援を改めてお願い申し上げます。
先日、休日を利用して気の向くままに書棚に飾ってあった創立百周年記念誌「凌霜百年」をめくってみました。いくつかの新しい発見と併せて、変革期を全力で乗り切り、次世代に繋いでいく責任の重さを改めて感じるひと時でした。
今まで会誌「凌霜386号」という数字をただ漠然と眺めていましたが、考えてみると、気の遠くなるような歳月と諸先輩の汗と涙の連続が今回の会誌に繋がっているのです。百周年記念誌の中で目にとまった記事をいくつかご紹介し、今一度凌霜会への想いを皆様と共有できればと考えます。
① “大正12年5月13日の開校20周年記念、昇格祝賀大会の春季総会において、同窓会 組織の強化を目指し社団法人化されることが決定された。名称は、「神戸興商会」と「凌霜会」の2案があり、後日支部及び常議員に照会、回答を求めたところ2対20で凌霜会に決定した(当時の学友会報175号)”とあり、当時の諸先輩の白熱した議論が今でも聞こえてくる。
② “昭和60年、当会顧問をお願いしていた新野先生が学長に就任され、3月25日の卒業式の式辞のなかで、高齢化、情報化の進む社会に臨むに当たっての心構えとして、「いうまでもなく、私たちは1人で生きていくことはできません。人と人との中で生き続けようとすると、何よりも自分以外の人々にとって存在してほしいヒトでなければなりません(凌霜第287号)”と述べられ、今日社会問題化している「無縁社会」に対する生き方の一端を約25年前に示されている。
③ “平成7年1月17日のあの忌まわしい大震災の1週間後、崩れた三宮の新聞会館の非常階段を登り、鉄パイプで石膏ボード製の壁に人ひとり潜れる穴をあける。金原君と2人リュックを背負い、両手に手提げ袋をもって搬出にかかる。翌日からは昨日の金原君のほか虎谷博臣、近藤寿夫の両君(3人とも34営)が手伝ってくれ、昨日準備しておいたダンボール7個を会館外に担ぎ出し…(凌霜第326号、堀事務局長震災日記)”とあり、目頭が熱くなるなど、まだまだご紹介したい記事は多々ありますが、紙面の関係で多くを割愛せざるを得ない点はご容赦下さい。会員の皆様が今一度「凌霜百年」に目を通されることを切望して止みません。
ところで、去る3月25日、母校の学位記授与式に臨席する機会がありました。華やかな内にも一抹の感傷を交えて淡々と進められた式典は、合唱団による校歌斉唱と応援団総部の卒業生諸君へのエールで閉式となりましたが、卒業以来51年ぶりに出席した私にとっては極めて印象に残るものでした。女子卒業生の多さと学部の広がりへの驚きは当然として、母校は国際都市「神戸」に在ってこそ、その輝きを放っているとの感を改めて強くしたところであります。神戸大学学歌には、まさに地域と大学の一体感溢れる歌詞が並んでおり、「神戸」という言葉が6回も出てくることを皆さんはご記憶でしょうか。
前号で、地元兵庫・神戸の歴史や母校の生い立ちについて、入学時の早い段階で学ぶ機会を、ぜひ大学にお考えいただきたいとの趣旨のことを書きましたが、今回の式典参列を機にその考えは間違っていないとの感を益々強くしたところであります。母校の歴史については全学共通授業科目の1つとして「神戸大学史」を既に開講していただいていますが、その背後にある「郷土の歴史」を新たに加えていただくことによって、「神戸大学史」講座が更に深みのあるものになると信じます。
「身近な同窓会」と「伝統的な母校愛」、この2つがうまく絡み合って、新しい時代環境に即した活力ある凌霜会が維持できると思っています。